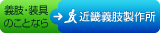頸損だより2006冬(No.100) 2007年1月27日発送
兵庫頸損連絡会だより 特別版
~「頸損だより」100号誌記念に寄せて~ 三戸呂 克美
先ずは、「頸損だより」100号発行おめでとうございます。年4回の発行で25年間。「継続は力なり」といいますが、ここまでこれたのは編集部長に就任された方のみならず原稿を寄稿された会員の皆様、それを支えた関係者の皆様の賜物だと思います。そして、近年特に大阪頸損連絡会の活動は活発になっています。これも機関誌の充実との相乗効果だと思います。
さて、大阪頸髄損傷者連絡会(「大阪頸損連絡会」と略す)が設立されて単純計算ですと25年が経つことになります。設立当事は頸損者の会といえば東京に頸髄損傷者連絡会(現、全国頸髄損傷者連絡会)がありました。そこで発行されていた機関誌「頸損」が唯一の(専門)情報誌でした。会員になると「頸損」が送られてきますが内容は東京中心のものでした。それでも、地方では考えられない新鮮な情報に別世界をみたことを思い出します。
その当時を振り返ってみると、当事者団体として活動している頸損者の会はまだ関西にはありませんし、もちろん大阪頸損連絡会はありませんでした。しかし、「頸損友の会」という名前で長居の身障者スポーツセンターを拠点に当事者が集まり近況を話し合い情報交換をしていました。
定期的に会合が持てるようになった時を見計らい当事者団体としての組織作りを行なう事になりました。「頸損友の会」から「大阪頸損連絡会」に名称を変更し、同時に全国頸損連絡会の大阪支部になりました。名称を変更し、会則を作り、事業・行事を定期的に行なうことになり機関誌も本格的に発行することになりました。
当時は今のように、パソコン、ワープロを誰もが持っているものではありません。タイプライターが主力の時代です。まして、インターネットなんて少数の人がすることぐらいにしか思っていなかった時代に「頸損だより」は発行を続けていました。しかし、その陰には並々ならぬ努力があったのです。
初代編集部長は坂上正司さん(現、全国副会長)でした。当事「頸損だより」の発行部数は20部ぐらいだったと思います。その後100部ぐらいまで伸びるのですが、印刷に出すお金もなく郵送料金が安くなる第3種の認可も取れていないとき、家庭用コピー機で両面コピーの「頸損だより」の発行を続けました。号を増すごとに増える内容の多さを封書用切手で送れるぎりぎりの重量にする工夫は一言では語れない苦労がありました。コピー用紙1枚の質や重量の選択、封筒の選択など出来るだけ必要な情報を多く皆さんに届ける為の苦労です。仕事の合間を見てコピーした「頸損だより」を1部1部綴じて封筒に詰める、いわゆる発送作業など一連のことをやり遂げれたことは坂上さんのお父様抜きには語れません。原稿依頼にも苦労がありました。仕上げた原稿を郵送し、手書きのものはタイプで打つかワープロで清書する。写真は切り貼りするがコピー機ではきれいに出ません。何とかもっと楽にしたい、家族の手を借りるのはよくない、という考えは誰もがもっていました。会員も順調に増え続ける中「頸損だより」の部数も伸びていきます。そしてついに念願であった、郵送費割引(第三種)の取得、印刷会社への製本外注にと踏み切ったのです。
今振り返ると外出にはヘルパー派遣も無く、会活動すべてにおいてボランティア、友人、家族の手を借りて行っていました。
また、会活動をみると今で言うバリアフリー調査は名前こそ違うが同じ事を行なっていました。例えば、車椅子で入れる店調査、利用できる鉄道駅アクセス調査などがあります。ちなみに、大阪頸損連絡会の恒例行事で「街に出よう」は調査を兼ねた行事でありそのままの形で現在も続いています。
昔と今ではどちらが良いかと問われれば、もちろん今が良いと答えます。しかし、満足しているかと聞かれれば答えはNOです。すべてがゼロから始まる我々の世界ですが、問題解決に向けて、壁が高ければ高いほど、長ければ長いほど、越える力や突き進む力を強くして進めば必ず崩すことができると信じています。やらずに悔いを残すよりやって後悔する方が人生楽しいと思います。満足できる社会を目指してこれからも動き続ける大阪頸損連絡会であって欲しいと願います。
「頸損だより」100号発行を記念して感無量の一時を今は亡き、劔持雄二 氏(初代事務局長)、谷内政夫 氏(第3代事務局長)、河野雄二 氏(河野進さんのお父様で郵便料金第3種取得にご尽力いただく)に捧げたい。
1993年、「大阪頸損連絡会オールスター秋の大運動会スペシャル」に参加する三戸呂さん(第48号、1993.12.30)