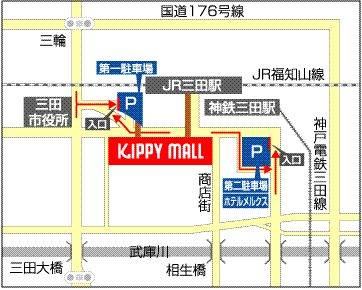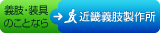ひとりじゃないよ–頚損解体新書-2010
これは単なる調査報告書ではない、重度頸髄損傷者の皆さんの宣言文である。
刊行の主旨も明快だ:
重度頸髄損傷者でも自立できる社会をめざして、「そのための社会的条件整備には何を対象として、どう手をつければよいか」を明らかにするために刊行した、とある。
頚髄損傷の医学的治療には、実態が明らかになった19世紀以来目立った進歩はない。僅かに頚椎の脱臼・骨折が直せるようになっただけである。損傷脊髄の修復は未だに全く手つかずのままである。再生医療に望みを託しているものの、治療として完成させるまでには道遠いものがある。
その一方で人工呼吸器を必要とする最重度(高位)の頚髄損傷者が自立できる時代がやってきた。ほかでもない介護・福祉制度が整備された結果である。リハビリテーション医学・医療の進歩が可能にしたのか、と言われると恥ずかしい。もっと突っ込んでいえば重度障害者(頚髄損傷者や脳性マヒ者)が体を張って国に圧力をかけた成果に他ならない。治療の術もない障害者であるから「当事者抜きに、障害者のことを決めるな」という正論を、国は認めざるをえなかったわけだ。心を一つにした車椅子の障害者団体を前にして、結局、社会的なハンディを軽減する政策が事態を救った!
重度頸髄損傷者の皆さんの調査は周到であった。1991年施行の前回調査の経験を踏まえ、比較によってこの間の“社会的条件整備”の進み具合を提示することができたのだ。
煩を厭わずに挙げてみよう:
- 1991年の第一回調査報告(19年前)とくらべる—世の中が変わったことも、変わらない実態も、今後の課題もより明らかだ
- 障害者の実態調査であると共に自立への社会的障壁を制度・介助者・就労などに分けて光を当てる
- 職場内や通勤のための介護を、保険制度は、認めていない
- ホームヘルパー(有償介助)と家族の介助がなければ自立は困難
- 頚髄損傷の専門医、脊髄損傷の拠点病院が今でも決定的に不足する
- 高齢化に伴う健康問題が深刻化する
- リハビリテーション工学が自立を目指す障害者に大きな支えとなる
刊行者(全国頸髄損傷者連絡会)の意図は成功したと思う。しかし、調査によってリハビリテーション医療と介護・福祉の乖離も明白になった。
現代のリハビリテーション医学・医療と介護・福祉の成り立ちはそもそも出発点から違う。後者が救貧法(16世紀イギリスに始まる)や労働者の傷病・休業補償制度(19世紀プロシャに始まる)に起源を持っているのに対してリハビリテーション医学・医療は20世紀の世界戦争に端を発する若い学問であり医療技術である。リハビリテーション医学・医療が個々の症例研究を基盤とする科学研究とその応用であるのに対して、介護・福祉は処遇や格差の政策的な是正にほかならない。しかし後者の対応が、実績の上では、確かに成功している。医学・医療の無力さが重度障害者を産み、この人たちが社会的条件整備(社会的正義)に向けて力を尽くす、という姿が浮かび上がる。
それでもこの人たちの真の願いは損傷脊髄の修復であるに違いない、と私の中の医療人は信じている。
今では連絡会の主要メンバーの一人として活躍するS君の立派な業績に敬意を表しながら、当時の主治医としては、やはり、直せなかったことが悔しい。
大阪保健医療大学学長
大阪大学医学部名誉教授
大阪厚生年金病院名誉院長
小野啓郎
リンクを追加2012.05.03
ひとりじゃないよ-頚損解体新書-2010 – 学長ブログ|大阪保健医療大学(OHSU)